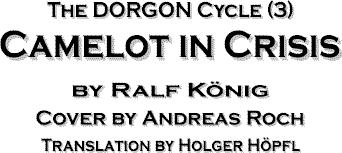|
||||||
ホーマー G. アダムスはオリンプのキャメロット オフィスの最後についてのニュースを伝えたシントロニクスのスイッチを切った。 腕を傷一つ無い机の上に重々しく横たえ、彼は深いため息をついた。過去からの イメージが彼の不死なる脳の中で閃いた。彼は長い人生の間に同じような状況に 直面せねばならなかった。そのため容易にオリンプの人々にとってどれほど恐ろしい 事であったか想像できた。そして、今彼のオリンプでの部下は皆死んでしまった。 不死者は机から離れ、展望窓に向かって歩いた。そこからキャメロットの首都の 良い景観が得られる。 新しい一日のきらめく空を静かに眺めながら、不死であることを繰り返し 罵った。同じような恐ろしい事件を繰り返し繰り返しくぐり抜けるか、少なくとも 彼の目の前に展開されるだけでなく、事件が起こるその度ごとに、人生ですでに 体験した同じ風景におそわれるのだ。 彼は背後に小さな物音を聞き振り返った。サム、小柄なソマール人が会議室から 出てきてホーマーの事務室にノックもせずに入ってきた。彼は外交官であるが、 予期できない行動でたえずホーマー G. アダムスを驚かしていた。彼のすぐ 後ろにはやせて長身のアウレク、サグギター人、が続いた。彼の顔は 堅い仮面のようで筋肉一つ動かしていなかった。 「みんな死んでしまった。」不死者は言った。 「こんなことが続くのか。何としてもこれを防がねば!」 小柄なソマール人は静かにうなずいた。アウレクは返答しなかった。彼らは ゆっくりと部屋を横切り、不死者の隣に立ち都市のパノラマを眺めた。サムは こうべをめぐらし、不死者を見つめた。 「本当にみんな死んだのですか?」彼は訊ねた。 アダムスはうなずいた。そして眼をそらしてため息をついた。 「ざんねんながら、すべてのオフィスを維持できない。つまり、キャメロット は他の世界と完全に切りはなされるということだ。どうしたらいい。 このままだともっと犠牲者は増え、私はそれに対してどうすることも 出来ない。」 彼は打ちのめされた様に見え、ソマ−ル人はしばしアダムスがこれを どう対処するのかと自問した。そのような高度の責任はアダムスの ごとき特別な人物にもおもすぎるように思われた。 ロ−ダンが第三勢力を設立した時にすでに彼の側にいた男は 友人たちが彼の側にいないことを残念に思った。 そのため彼があらゆる事に対する責任を負わねばならないのだ。 「アリエス(ARIES)の時代みたいだ。」彼はつぶやいた。 「アリエス?」アウレクは不審そうに繰り返した。サグギタ−人 はアダムスを知ってから数日しか経っていなく、この言葉が何を意味するのか 知らなかった。しかし、その瞬間テラナ−は窓から向きを変えたので説明を 待つ必要は無かった。彼は肩をいからし、深い息をつくと、 新たにエネルギ−を得たかのように彼の机に戻った。彼は重々しく 腰を下ろし、椅子は所有者の体重をクッションに乗せた。 そして、彼はビデオフォンシステムを起動した。 「今、何が起こっているのですか?」サムはアダムスのほうに歩みながら たずねた。不死者は彼をちらと眺めると、スクリ−ンに注意を戻した。 「は?」ソマ−ル人にはスクリ−ンはみえず、声だけが聞こえた。 「直ちに全キャメロットオフィスに最高警報を命じよ。人々にこの種の 襲撃がどこででも再び起こりうることを指摘せよ。必要なら オフィスのスタッフは直ちに逃走せよ。選択の余地がなければ 自衛してもらわねばならない。ありとあらゆる手段を用いて。」 サムは何も聞いておらず、テラナ−の対話者がしぶしぶうなずいている のであろうと思った。ソマ−ル人は容易にこれを理解できた。不死者の 薄灰色な目は外交官が好まないという印象を示している。 彼は今まさに虚構の敵対者につかみ掛からんばかりの印象を受けた。 小柄なソマール人はここに留まるのが懸命かどうか考えはじめた。 しかし、その時、彼はアダムスに元々期待していたことを思い出し、 デスクの反対側の椅子に腰掛けた。 家具はただちに反応して少しだけ椅子を持ち上げ、ソマール人が机の上が 見えるようにした。その様なサポートはアウレクには不要であった。 サグギター人は腰を下ろし、静かに会話を追った。 「本当にLFTの惑星の一つで軍事行動を起こすリスクを冒すつもりですか?」 アダムスは目を上げしばらくその大使を見た。それから彼はため息をついて 同意してうなずいた。 「君の言うとおり。これは危険なことだ。しかし、外の者達はすでに 軍事衝突に巻きこなれているんだ。この場合、LFTと我々は共通の敵を 持っているわけだ。我々のスタッフが命を守ろうとするなら、LFTは 文句を言うまいと思うがね。」 サムは同意した。彼はこの見方をたやすく追いかけることが出来たが、 大使としての彼の仕事はいかなる種類の議論や抗争を先回りして防ぐこと にあり、硬派路線を支持することではなかった。 他方で、アダムスがかれ自身と同じくらい高いモラルの考えを持つ テラナーであることも明らかだ。だから、彼が武力の使用を命ずるなら 事態はそこまで悪化していることにほかならない。 「状況は本当にそれほど絶望的なのですか?」彼はたずねた。 アダムスはうなずいただけであった。 「君に写真をわけてあげよう。ともかく、多数の人々が命を失った。このことは 耐えられない。我々を恐怖と共におそったこの組織は、確かにキャメロットが これまでに出くわした最大の脅威だ。人類やギャラクティウム(Galacticum)の あらゆる権力グループと言えどもこれほどまでに危険ではありえなかった。 結局のところ、彼らについてなら我々は良く知っている。しかし、モードレッド は完全に違う。それはキャメロットの最後を意味するかもしれないのだ。」 これはそのテラナーにとっては何時に無く長いスピーチであった。このように ゆっくりとしかし確実に、ソマール人はここで何か起こるに違いないかを 理解し始めた。おそらく小柄なために、テラの白頭ワシに良く似た、 ジオン・ジム(Siom Som)銀河からの地球外生命体はしばし思索にふけって 我を忘れた。そしてテラナーの目を真っすぐのぞき込んで、 「あなたがたを援助しましょう。このモードレッドという組織についてもっと 知らねばなりません。あなたの言うとおり、既知の敵はその起源さえ不明な ものよりずっと対処しやすいものです。」 「君の提案は何かね?」テラナーは少し前に身体を傾けた。 「誰かをスティフターマンIII(Stiftermann III)に派遣することを提案します。 きっと<バジス(BASIS)>で有用な情報を多数集められるでしょう。結局のところ、 モードレッドは背後で行動する組織です。おそらく彼らはギャラクティック ガーディアン(Galactic Guardians)とコンタクトがあるんではないでしょうか?」 「悪くない考えだ。誰が適任かね?」 「実のところ私が自分でやりたいと思います。おそらくそこで我々を助けてくれる であろう人物に心当たりがあります。」 アダムスの顔つきが非常な敬意を表していた。「君が他の銀河から来たと言う事実を 考えると、ここでうまく身を守るだろう。解った。直ちに出発してくれると 非常に助かる。そして、・・・良い結果を持ち帰ってくれ。」 その瞬間、アウレクの声が上がった。 「サグギター人の支援を提供しましょう。<サグリトン>を送って私の故郷銀河 から艦隊を呼び寄せましょう。適切な時間内に彼らが船をつれて戻ると保証は 出来ませんが、そうなるように彼らが全力を尽くすことは知っています。その間、 私はここキャメロットであなたを支援しましょう。我々はチームを組んで 新兵募集の事務所の支援のために派遣することが出来るでしょう。私はこれらの チームの組織で助けになると思います。」 感動してテラナ−は顔をほころばせた。「我々の内部問題に何等関わりのない 二種属からこれほどの援助を受けるとは。」息を吐き出して彼は後ろにもたれた。 「これほどまでに高い責任感のある種属が我々の銀河にいればなあ。しかし 今のところ、我々は此処では殆ど独りぼっちだ。君たちの援助は多いに 感謝するよ。」テラナ−は彼ら二人に頷いた。 ソマ−ル人は頷き返して立ち上がった。アダムスは彼が机をまわって やってくるのを待ち受けた。今彼らの目は同じ高さにあった。アダムスは 手を伸ばし、その生物は固く握った。 「幸運を。」テラナ−は祈った。 アウレクはドアの所に達した。そして振り向いた。 「衛星軌道の我々の船に行って、個人的な準備をしようと思います。」 アダムスは彼に頷いた。 「スペ−スジェットを自由に使って君の船まで行くといい。それから 我々の全主要スタッフメンバ−に、君が我々の危機の防衛のための命令を 帯びていると伝えておこう。」 不死者の顔は責任感と感謝を表わしていた。アウレクとアダムスが知り合ってから 短い時間しか経っていないが、新たな友情が始まったのは明らかだった。 無言でサムは向きを変えた。本名スルエル・アルロク・モク( Sruel Allok Mok)は確かな 足取りでドアに向かって歩いていった。見かけは小柄であるが、彼は 外見において欠けている様に見えるものを勇気ある行動で示した。 アダムスは心の中でこの付加的事実についてロ−ダンを祝った。ペリ−の おかげでサムはキャメロット組織のメンバ−になったのだ。そして 幾度となく優秀なメンバ−であることを証明したのだ。彼の外交官としての 能力は今回のケ−スでは大いに役立ち、彼らが必要としている 成果をもたらしてくれるだろう。 ドアが閉まった時、テラナ−は立上り、再び窓の所に歩んだ。 手を後ろに組み、深く息をした。太陽は空高くにあり、アダムスの心も 同じく高揚しているかのようであった。わずか数分前に比べ、その日の 印象は幾分良くなった。 願わくば、速やかに彼らがこの脅威の実体をとらえてくれることを。 彼らはすでに十分過ぎるほどの困難と悲しみを負っているのだ。
アウレクは彼の宇宙船の艦橋に立って士官達の目をひたと 見据えた。 「諸君、大きな問題が生じた。」 ゆっくりと彼は皆を順々に見た。 「モ−ドレッドと呼ばれる組織がキャメロットの友人達に多大な困難と損害 を与えている。私はこの敵との戦いに我々の援助を申出て、キャメロットは 受け入れた。そこで、我々は最寄の前哨基地まで<サグリトン>で飛び 本国からの支援を命ずる予定だ。」 アウレクは何人かの顔に熱意が全く欠けているのを見て取った。 「もっと正確には、諸君らがこの任務を果たすのだ。私は此処で友人達の 戦いを援助するために必要とされている。」 再び言葉に効力を与えるため彼はしばし話すのを休止した。彼の代理、 セラカン船長(captain Serakan)は落ち着かない顔つきを示した。彼は <サグリトン>の戦力のサポ−トなしに指揮官をキャメッロトに 残すことに強い不快感を示した。しかし、感情はいかに嫌々であれ、彼の 義務は上官に服従することを求めた。 アウレクは続けた。 「最寄の連絡基地まで1000万光年離れている。私は諸君が時間内に援助を 求めて此処に戻ってこれるかどうかは判らない。しかし、諸君らを 信頼している。機関の許す限り最高速で飛行せよ。」 「サー、責任感に基づいてお尋ねしおます。これはテラナ−の内政問題にすぎ ません。我々が何をしなければならないというのでしょうか?」 セラカンは反対意見を投じて知ろうとした。 アウレクは近くに歩み寄り、彼の目を真直ぐに見据えた。 「セラカン、5年前にペリ−・ロ−ダンがドルファス(Dolphus)と カオタ−ク(Chaotarcs)から我々の銀河を救ったことを覚えているな。 いまこそ、我々の恩義を返す時だ。」 セラカンは沈黙し、上官の命令に従った。 「そして、友よ、しばしさらばだ。いつものようにそつ無く任務を果たしてくれ。」 彼はセラカンを鋭く見すえた。「サラカン船長、私はこれより<サグリトン> の指揮権を貴官に委譲する。」 セラカンは命令を受け、黙って向きを変えた。彼は指令席に腰を下ろした。 アウレクは巨船の指令室を離れ、格納庫の一つに足を進めた。 彼は静かに<サグリトン>の中を歩いた。彼の最も愛した場所のいくつかに 別れを告げるためにそこかしこで立ち止まりながら。次に何時彼の船を 眼にするかはわからない。ひょっとすると永久にないかも・・・。 しかし、とうとう彼は格納庫に着いた。ドアが開いたとき、彼は自分を キャメロットに送り届けるはずのスペースジェットに乗り込む前に これを最後と辺りを見回した。 命令は発せられた。指揮権は船長に委譲された。彼のここでの仕事は 終わった。 ゆっくりと、ほとんど渋々という感じで、アウレクはタラップに足をかけ、 ジェット内部に姿を消した。彼はパイロットの隣の席に身を沈めた。 ヘッドフォンを身につけ、艦橋との通話を開始した。 「艦橋へ、こちらスペースジェット。開錠準備完了。」 「了解、スペースジェット。開錠を許可する。」 彼の船長の声はの自身の気持ちについて何も示していなかった。しかし、 それは全く必要なかった。アウレクはセラカンの眼を見て、彼がまだ 指揮官の決定に不服である様子を知った。 一瞬のほほ笑みが彼の唇に浮かんだ。彼は乗員の忠誠心が決して 無くならないことを知っていた。そのようなグループを指揮することが 出来てアウレクは幸せを感じていた。 アウレクはパイロットにうなずき、彼はボタンを押した。 警報サイレンが格納庫にひびきわたった。ふんわりとジェットは エネルギー場のクッションで持ち上げられ、ゆっくり開いた 上げ扉に向かって滑空していった。 別のエネルギー場が大気の漏れを防いでいた。ジェットはますます広がる 開口部に向かって滑空し、ようやくそこに到着した。 小型宇宙船がエネルギー場に触れたとき、ジェットを通すのに 十分な構造亀裂が形成された。宇宙船の背後で 上げ扉は再びゆっくりと閉じ始めた。 アウレクは後部スクリーンを見て、船のドアがゆっくり下がっていく様を 観察した。船の光で照らされたすき間はだんだん小さくなって、 最後には完全に閉じた。船の外壁は宇宙の暗黒の中で姿を消した。 エンジンが起動し、ジェットは巨船から離れ、ゆっくりと速さを増した。 真正面に惑星の球体が視界に入ってきた。キャメロットは一部欠けて見えたが、 この比較的近距離からでも、この地球に似た惑星の美しさが容易に見て取れる。 実際、不死者たちは良い選択をしたものだ。 宇宙でのこの瞬間、特に今のような小型船に乗っている時、は 宇宙飛行士が期待しうる最も美しいものの一つであった。 アウレクの種族が宇宙飛行をマスターしてから何世紀も経っているにも かかわらず、宇宙飛行士はいつも目標惑星の最初の微光を驚異をもって 見つめるものだ。 アウレクはこのしばしの夢見心地を愉しんだ。 そして、彼の視線は後方スクリーンをさまよった。頂点に塔を持った 巨大円盤がゆっくり縮まっていき、ジェットが円盤の水平線の下に潜った時、 塔はもはや見えなくなった。 今や彼らは推進機関を眺めており、その内部は既に微光を発していた。 ジェットが必要な安全距離に到達したとき、微光は殆ど耐えられない 位になっており、そしてエンジンが点火した。 <サグリトン>は発進し、だんだん小さくなって、最後には小さな輝点が 見えるだけになった。最後には、それもまた宇宙の深淵に消えてしまった。 「幸運を。」とサグギタ−人はつぶやいた。 そして彼は惑星に関心を戻した。「着陸までどれくらいかかる?」 「丁度18分と30秒です。」 アウレクは頷いて後ろにもたれた。惑星の表面にゆっくりと近づく間 操縦士の通常操作をみるともなく眺めていた。ジェットが大気圏に深く入った 時、防御シ−ルドが張られ小型船は速度を落とした。スクリ−ンの輝きは、 宇宙の暗黒がキャメロットの早朝の明るさに しだいに取って代わられるうちに減少して いった。眼下では都市が次第に大きくなっていった。慣れた手つきで 操縦士はキャメロットの宇宙港に接近していった。数分後、スペ−スジェット は着陸した。 アウレクはアダムスとの映像通信を開き、30分以内に到着することを 伝えた。 宇宙空港の主ビルディングに入るとき、彼はホールをゆっくり動いている ソマール人のシルエットを認めた。歩みを止め、彼は方向を変えた。 「サム」その生物がホールをまさに出ようとしている時、彼は呼びかけた。 相手はアウレクに向き直り、僅かにくちばしをゆがめた。これは微笑で あろうか?アウレクはそのジェスチャーに応じた。 「今から出発?」 「さっき言った通り。」 「昔の様にペリーがここに居ないのは残念だ。 <サグリトン>を救援要請に送り出したところだ。間に合ううちに船が 任務を果してくれることを願っている。」 「それはいい。私はモードレッドの化け物を何処に見つけるべきか 突き止めて、君がやつらをやっつける。これこそ本当の仕事分担ですね。」 その生物は甲高い笑い声を発した。「失礼。私の船はもうすぐ出発するので。」 ソマ−ル人は身を翻そうとしたが、アウレクは彼の背を捕まえた。 「一体全体、アリエス(ARIES)とは何だ?アダムスはこの言葉を使っていたが。」 「カンタロ−(Cantaro)支配時代の抵抗グル−プだ。アダムスは暫くの間 これら抵抗闘争の指導者だったのさ。」 アウレクは了解した風に頷いた.この度は彼はサムの背を捕まえず 再び向きを変えて離れるにまかせた.この数語で全てがかたり尽くされた かのようであった.サグギタ−人は小柄な生物がホ−ルを離れるまで しばし観測していた.そしてアウレクもまた考え込みながら向きを 変え,宇宙空港の歓迎ホ−ルを後にし主入口に待機していた タクシ−を捕まえた. 「政府ビル.」彼は心そこに無い風につぶやいた.彼は出発を 命じたが,本当は注意を払っていなかった.ソマ−ル人は正しい. 彼らがたまたま巻き込まれたのは馴染みのない状況で, ジオンゾム(Siom Som)からの生物やサグギタ−人が解決 せねばならない.不死者たちはみんな何処に居るのだろうか? ひょっとしたら彼らの幾人かは命を落とし,他の幾人かは 大宇宙の深渕で行方不明になったり人類を救う任務に従事して いたのだろう.しかし,おそらくある時点では自分たちの 本当の出身地を思い出すべきであったろう. 未だギャラクシアンの故郷で数多くの事件が起こり,彼らの 大部分が不在なら銀河系を打ち負かすため巨大な勢力が 現れるかもしれない. 他方、人類はゆっくりと、しかし確実に自らを救うのに足りるほど 円熟せねばならない。これら人類は不死者たちからの開放を願ったのでは なかったのか?それなのに、トラブルの時は 当然のように不死者たちのサポートを受け入れるのか? 信じられない、そして不死者たちがこの態度に困惑していないという事実は もっと信じられない。 この銀河系、天の河では数多くの不吉な事件が起こり続けていて、 多くのグループが銀河系における安定をもたらす唯一の権力 基盤として、今日までキャメロットをみなしている。 のぞむらくはアダムスが銀河外生物の助けで最悪の事態が起こるのを 防ぐことが出来るかもしれない。それは全く皮肉なことだ。 異銀河からの生物は、バランスを模索しているこの銀河系内の 唯一の権力基盤を助ける途上にあるというのは。 アウレクは乗り物が僅かに傾いたのに気が付いた。彼は目的地に 着いていた。タクシーを出て、直に1時間ほど前に サムとアダムスと会談していた部屋に入った。 アウレクはその外交官が使っていた同じ椅子に身を沈めた。
「アウレク, 我々は自分の問題で手いっぱいだよ。」 アダムスは再び椅子から立上り机を回って歩いてきた。彼は机の角に腰掛け サグギタ−人に視線を定めた。「<サグリトン>が間に合ううちに戻ってくる とは思えない。が、少なくとも今は一縷の望みはあるわけだ。いずれにせよ、船が 戻るまでにキャメロットの事務所の守りを固めないと。この瞬間にも敵は攻撃するやも しれん。サムは、<バジス>を探るために出発した。」 アウレクは頷いた。「彼が出発する前に宇宙港で会いました。今の状況を あなたがARIES抵抗グル−プを指揮していた時代と比べてみましたか?」 アダムスはこの質問に殆どいぶからなかった。アウレクは非常に 賢明で、知らないことがあると必要な情報を得るため時間を無駄に することはしなかった。「いいや。しかし、私の状況は非常に似ているかな。 私はここで一人事態の責任をにない、友人たちは再び大宇宙の焦点にいる。」 アウレクはにやりとした。「あなたは本当は自分が冒険旅行に 生きたくはなかったのですか?この銀河系で起こっていること だけでは満足ではないのでしょう?」 「確かに。しかし、これはつまらない行動だな。私はペリーの行動と もっと寄り添った何かで働きたい。」アダムスは沈黙し、そしてにやりとした。 「いや。本当のところ、そんなことは望まない。おそらく、我々は もっと重要なことを分担すべきなのだろう。キャメロット事務所に警戒警報を 発するだけではとても十分とは言えないと思う。何か有効な手が打てれば。」 考えぶかげに彼はあごをこすり、そして視線をサグギター人に向けた。 「我々の事務所を守る戦闘部隊についてもう話したね。戦闘経験のある 人をそこに、熱線銃を撃ったことのある人を射撃台以外の場所に派遣 するのがずっと良いと思うのだが。」 アウレクは頭をうなずいて立ち上がった。「その手配をしましょう。」 「ありがとう。君には白紙の委任状をわたそう。 私はパオラ・ダシュマガン(Paola Daschmagan)やシストロ・カンと コンタクトをとらざるを得なかった。彼らは公式に我々が事務所を 守るためにLFTの惑星に宇宙船を派遣するのを認めてくれた。 彼らは我々のために旧植民惑星との仲介も約束してくれた。 残念ながら、これで我々の事務所の所在を明らかにしなければ ならなくなった。」ため息をついて、不死者は自分の椅子に 倒れこみ、目の前のデータパッドをつかんだ。 これらの言葉は彼の信頼の紛れもない証拠であった。 なぜなら彼らは知り合ってからそれほど時間が経っていないというのに。 しかし、ペリーが信頼した人物なら財務の天才も信用するだろう。 しばらく彼はデータを見、それからサグギター人に視線を戻した。 「全く奇妙なものだな、ソマール人とサグギター人がキャメロットを 救うために立ち上がってくれるとは。 アウレクが頷いた。「私にも考えがあります。 実のところ、我々はたまたま、この特別な瞬間にここに居たにすぎません。 さらに、我々は例え望んでもモードレッドから身を隠すことさえ できません。さらに、我々はここにいるのだから、テロ組織は 撃つ相手を一々選ぶほどおめでたくはないでしょう。 つまり、我々は一蓮托生というわけです。ペリーならサグギター のためにまさに同じ事をしてくれるでしょう。 だから私を使って下さい。」 決然として彼は向きを変え、後ろを振り返る事無く事務室を出ていった。 アダムスは、すでに閉じたドアをしばしみつめた。攻撃の詳細を報じている デ−タパッドに注意を戻す前にかすかにかぶりを振った。失望して パッドを机に投げ椅子を回した。太陽はすでに天頂に達していた。 一瞬ごとに不死者の心配は増加した。彼が待機しているこの瞬間にも 悪い知らせが銀河系から届いていた。 「全くすばらしい、この惑星は。」カスカルはカウチに 寝そべり腕を頭の後ろで組んだ。彼はサンダル・ト−ク、過去からの 寡黙な友人、をちらと眺めた。蛮人は机に腰掛け、愛用の弓は傍らで 机にもたれかせていた。彼はカスカルに返答せず、ニュ−スを聞くのに 集中していた。キャメロット・オンラインは銀河系の主要事件を 皆に伝えていた。 カスカルは肩をすくめて天井に視線を向けた。突然彼は頭を持ち上げてついには 完全に直立した。 「...キャメロット事務所への引き続いた攻撃について報告します。 すでに報じられたように、オリンプにおける我々の募集事務所が 未知の敵に攻撃されキャメロット人スタッフ全員が死亡しました。 モ−ドレッドと自称している未知のテロリストグル−プはこの犯行に 対する声明を報じています。只今からテロリストたちからの声明を 伝えます...」 一つの紋章がスクリ−ンに現れたが、これまでカスカルが見た事ない ものであった。組織の目的を詳しく述べている声が聞き取れた。他ならぬ 細胞活性装置保持者たちと彼らの基地キャメロットの抹消がこれら テロリストたちの計画であった。報告が続いている間、ト−クの顔色 は変わらず、オリンプの事務所の恐ろしい場面がわずかに色あせた 映像で流れた時にわずかに引きつらせた。けれども公報が終わると、 彼は弓をつかんで凄みのある顔で立ち上がった。 「で、一体何をするつもりかわかっているのかね?」カスカルは立ち上がり、 この誇り高き男を引き止めようとした。 「アダムスの所に行く。彼は助けを必要としているだろう。」束の間、 ト−クの顔の氷のような表情がカスカルの目に突き刺さった。そして サンダルは向きを変えた。 カスカルは友の回りを回った。彼は視線をサンダル・ト−クに注いで 彼を立ち止まらせた。「私ぬきで出かけて楽しめると本当に考えている なら、君は全く間違っている。」 ト−クは彼の視線を受け止め、そして頷いた。「来たれ、テラから 来た男よ。<タクヴァリオン>の離陸準備にかかろう。 ト−クは弓を肩にかけ、そして彼らは並んで部屋を出て宇宙船に 向かった。そこに着く前に、彼らはサグギタ−人アウレクに 出会った。彼は無言で合図をして近寄った。 「状況は?」カスカルは容易にペ−スを保ったが、エクスト・アルファ から来た野蛮人は少し不満顔であった。 「攻撃のことは聞いているな?」 カスカルとト−クは同意の印に頷いた。 「我々は反撃する予定だ。今アダムスの命令で異なるキャメロット事務所に 派遣するコマンド部隊を編成している。手伝って くれないか?」 「手伝いはご免だ、闘いたいんだ。」ト−クは答えた。彼は弓を振り 怒りをあらわにした。 サグギタ−人は歯を見せた。このテラナ−ときたら、と彼は考えた。 彼らは大宇宙の危険と対決すること以外に何も望まないと言われているが、 彼らはちょっとした戦いに背を向ける事はないのだな。この種属がこれほど 急速に発展したというのはちょっとした驚きだ。彼はト−クが エクスト・アルファから来たことを忘れているようであった。 「問題ない。基地の一つをまかそう。ほかに特別な希望は?」 カスカルは頭を振ったが、すぐに顔を上げた。 「もし我々がもう火消し部隊に組み込まれているなら、プロフォスを 選びたい。昔、そこで一人の少女を知っていた。おそらく彼女の 曽々々々々々々々孫に会えるだろうか?」 トークは頭を後ろにそらし、大笑いをはじめた。かれは親友の肩を 軽く叩いてサグギター人から向きを変え、一緒に歩き出した。 「<タクヴァリオン>の発進準備をして、それから出発する。 我々のために指を曲げて重ねておいてくれ!(訳注:幸運をまねく おまじないの意味。)」 アウレクは手を尻にのせて頭を振った。カスカルはこの頭の動作を 視線のすみでとらえたが、これにより冷静になった。 オリンプでの事件を思うと笑いを口に浮かべるのは難しくなった。 とはいえ、うちひしがれた気分で居ることは事態の改善にはならない。 未来は目の前にあり、過去に打ち負かされてはならない。 恐怖は長くは彼を縛り付けない。もしそうだったら、彼がゼロ時間デフォルメーター で過去に旅したときにカピンと出会うことはなかっただろう。 そして、彼がグルエルフィンについて知ることも、 <ロンドンII>で血に飢えたカサロとミンドロスのプロトン( Casaro and Prothon of Mindros)を打ち破ることもなかっただろう。 いや、彼は自らを脅えたままにすることはないであろう。 例え古い伝説からその由来を引き継いだ様に見える組織に対しても。 モードレッドはアーサー王の敵対者であった。不幸にも王の息子でもあった。 彼らの王、ペリー・ローダンは今はここにいない。しかし、彼の家臣達が そのような状況に対処出来なれけばならない。 カスカルは傍らのトークに視線を投げた。 彼はどのような役割を演じるのであろうか?ガラハド卿(Sir Galahad)? そして彼はランスロット(Lancelot)になるのであろうか? くすくす笑いながら。彼はグライダーで溢れた駐車場に着いたことに 気が付いた。トークは助手席に飛び乗り、運転席を親友のために残していた。 ため息をついて、テラナーはその乗り物の緩衝席に座って、エンジンをかけた。 きいっという衝撃波をのこしてグライダーは離陸した。宇宙空港は ほんの少し離れたところにあった。
蛮人は、無鉄砲な離陸の圧力がおさまると 姿勢を整えた。 彼はマイクをつかむと<タクヴァリオン>乗員の周波数に調整した。 そして、緊急警報を送った。 「連中が船に戻るまでにどれくらいかかるか拝見しよう。」 カスカルは横目で彼を見て、そして道に注意を戻した。「警報を送ったな。なぜだ?」 「連中が実際のところどんな風に過ごしているか知りたくてね。 あと数日もすればドンパチがあるでしょうから。」 カスカルは頷き、グライダーを宇宙港エリアのフェンスを飛び越えさせた。 「未確認グライダーに告ぐ、直ちに身元を明らかにしなさい。接近は禁止 されています。」甲高い声が送信されてきた。 トークはマイクをつかみ身分を明かした。 「こちら、<タクヴァリオン>の副司令。我々は警報下にある。 船は緊急発進の準備をする必要がある。」彼はにやりとして マイクを戻し、それ以上の呼びかけには無視した。 「警報についてのニュースは入っていません。何が起こっているのですか? 明らかにしなさい。」 カスカルは黙って運転を続け、1隻のジェットの周りを急旋回し、グライダーを 宇宙港の軍事エリアの後方部にそびえる巨大な球形に向けた。 近づくにつれてインターコスモで書かれた文字が識別出来るようになった。
<タクヴァリオン>は1000メートルの高さにそびえていた。 昔の<マルコ・ポーロ>には並ぶべくもないが、今日ではそのような 巨船は建造されていない。今日の搭載艇の能力は昨日のより大きな船の パワーを軽く凌駕していて、通常の規格(contigent?)の搭載艇を配備した 通常サイズの船は瞬時にちょっとした小艦隊を形成することができる。 この船はトークとカスカルのようなデュオにぴったりであった。 この空飛ぶ宝石の指揮官は、エアーロックを抜けて メタグラヴエンジン(metagrav propulsion)と 重火器を備えた赤道環にある格納庫にグライダーを進めた。 中枢部への最短通路であった。 カスカルはエンジンを唸らせながら最大出力で減速し、 ホール背後でグライダーを停止させた。 乗り物が止まりきらないうちにグライダーの 両側のドアが開き、二人の指揮官達は飛び出した。 時間を無駄にする事無く格納庫を飛びだし中枢部に直結する 移動ベルトに飛び乗った。 1分後、彼らは船のまさに中心にあるドーム型の部屋に着いた。 当惑して彼らは立ち止まり、辺りを見回した。 全乗員がそこにいた、みんなが位置についていた。 カスカルが入っていくと、船の第一士官の コリーネ・コン(Coreene Quon)が司令席から立ち上がった。 スリムな若い女性は指揮官に歩み寄った。 「サー、<タクヴァリオン>乗員は全員揃っています。船はいつでも離陸 できます。命令をお待ちしております、サー!」 カスカルはしばらく動かなかった、乗員達の素早さに驚いて。 トークが彼を軽く小突いてから初めて彼は反応した。 「よし、訓練終了。」 彼は大声で吹き出し、トークに向き合った。 「これでは、我々テラナーを退化人の集まりと呼ぶ奴がでるわけだ。 離陸から一々言わなければならんのか? 言ったらやつらはやってくれるのだろうな。」 無線で彼は全乗員に話し始めた。 「注目願おう、これは演習ではない。我々は1時間以内にプロフォスに 出発する。現地のキャメロット代理人たちの援軍として指名された。 諸君ら全て知っての通り、彼らは攻撃下にある。我々はプロフォスを 守るのだ。他の部隊は我々と同様に他の惑星に飛んで同じ任務にあたる ことになろう。」 「繰り返す。これは演習ではない。おそらく近いうちに戦闘になるだろう。 全乗員は引き続き警戒体制で待機せよ。全部署はさしあたり通常レベル(?、 regular contigent)で運用すること。 緊急通信、終わり。」 その間、トークは彼の傍らに歩み寄った。司令官を待ちながら、 彼は合成弓を手に取り、特殊矢で満たした矢筒を開け、 これらをカード机の手の届く位置に置いた。 そして向きを変え腕を胸の前で組んで静かに立ち上がった。 ようやく司令官は向きを変え彼に歩み寄った。 「指揮を引き継いでくれ、サンダル。すぐに戻るから。」 意味ぶかげな笑いを浮かべて彼は向きを変え、後ろも見ずに部屋を出た。 トークの顔は無表情のままであった。「アイアイ、サー。」彼は叫ぶと、 コンの空けた椅子に歩み腰を下ろした。 彼は艦橋乗員の顔色を無視した。 二人の過去から来た変わり者を知ったときの興味に満ちた顔色を。 彼らはそのようなふるまいに慣れ始めていたのだ。 「状況はどうだ?」 コンはコンソールに向き直り、各部門からの報告を待った。 「船は離陸可能です、サー。命令をお待ちしております。」 トークは頷き、メインスクリーンに向かった。そこでは宇宙空港の 軍事セクターが写されていた。彼はドアが開いて司令が部屋に 入ってくるまで辛抱強く待った。そして静かに立ち上がり短い報告を して席を離れた。
カスカルは司令席に腰を下ろし、肘掛けのボタンを押した。 小型ディスプレイがせり上がり、船の状態を司令官に示した。 全てのセクションが離陸準備完了を報告したが、彼はすでにそれを知っていた。 数秒間眼を閉じ、再び船を指揮する気分を味わった。 再び眼を開けて、彼は副官に向き直った。「サンダル、ここからずらかるぞ!」 「アイアイ、サー!」 時折彼らは古い習慣に陥る。 カスカルはもやは誰も公的な申告をしていない事を良く知っているが、 彼ら二人は社会通念を逸脱することを愉しんでいた。 そして彼が名前の指揮体系の価値がまだ存在していた時代を 懐かしんでいるという事実もある。 そして、そのため彼は自分の船にそのような指揮体系を導入したのだ。 これにより彼は故郷に帰ったかのような気分を感じる事が出来る。 そして、更に彼にはこのゲームを行うことに同意してくれた乗員を 持つという幸運もあった。かれらは新しい組織を受け入れ、 時空のひだに落下する前の時代と同様に考え行動することを 可能にした。 トークは船長の命令に対する行動に示されている様に、 この船で唯一この振るまいが本当に存在したことを 知っている。おそらく、そこには一種の皮肉もあったとは言え。 カスカルは友の反応に感謝していた。これが船の残りの 乗員にとってどのように振る舞うかを期待されているかの 良い手本になると感じていたので。 カスカルはエクソタアルファでの蛮人との共同統治の古きよき 日々の記憶をもの憂げに押しやった。かつてはトークは エクソタアルファの執政官であったのだ。そのような世界は もはや見つけることは出来ない。他の全てのものも変わって しまったのだ。 テラナーは自分たちがこれからの日々におそらく無用であると 証明されるであろう体験という荷物を持っていることを知っていた。 不死者達ほど老齢ではないものの、彼らはローダンの傍らで 多くの挑戦に対面し克服してきた。 さらに、彼らは今日では忘れさられたような方法で 事態を解決したのだ。 トークは宇宙港の管制塔に繋いだ。 「戦艦<タクヴァリオン>発進準備完了。離陸許可を求めます。」 不機嫌さをかくそうともしない声が聞こえた。 彼らがキャメロットにしばらく滞在していたとはいえ、 その惑星は大きく住民も多いため誰もが知り合いになれるわけではない。 明らかに宇宙空港のこの職員は彼らのことをまだ知らない様であった。 「発進してよろしい。」彼は告げた。「前方視界良好。 他の船を遮る恐れなし。」 カスカルは目を丸くした。 彼の時代では、そんなアナウンスをしたら 役立たずの牧師としてエアロックから、もちろん宇宙服を着せて、 投げ出され何光年も曳航されたものだった。 カスカルはこの事実を受け入れねばならないことを知っていたので、 唇をかみしめてプライドを押さえ、エンジンのウォームアップを 終えたトークに意識を集中した。 ゆっくりと戦艦は巨大な反重力機構の地からで大気中に浮かび上がった。 船はキャメロットの大気に向かっておもむろに加速し始めた。 地表の曲率が目立ち始め、惑星の大気圏を離れるやいなや、突然 辺りが暗くなった。 うっとりとカスカルは船の出発の様を観察していた。 彼は再びこの宇宙船の巨大な力を感じていた。 これは現実だと彼は考えた。宇宙に属さないとるに足らない 模造品の一つではなくて。 自由空間に到達した時、船はその本質をあらわにした。 操縦士はエンジンの出力を半分解放し、およそ600 km/sec2 に達した。 彼らがスピードを上げて上昇していくに連れて惑星は急速に縮んで行くようで あった。船が光速に接近しプロフォスにコースを定めた時、 面白そうにテラナーは後ろにもたれ、飛行を愉しんだ。 心配するな、友よ、テラナーは考えた。すぐ行く! 彼が守るために急行している惑星に既に災厄がゆっくりと接近しているとは 知るすべもなかった。もし知っていれば、船がメタグラヴ(metagrav)推進を 起動したとき、彼はそれほど冷静にはいられなかったであろう。 船は擬ブラックホールに引き寄せられ、光速の壁を越えた。ますます速く 彼らはキャメロットを離れ、銀河系の脅威の一つと対面するために 飛行を続けた。
彼女は窓の外を見た。うんざりと その日の終わりを待ち焦がれて。彼女の仕事はそれほど重いものではなく、 今日のように部屋に入ってくる人が居ないときは、まったくうんざりする のが常であった。 彼女は実際に何かをせずにディスクワークの一日を愉しめるような タイプの人間ではなかった。実際は全く逆であった。彼女は前の机に 広げた本に視線を下げ、この日を生き延びようとした。 「ホイスラーカンパニーにおけるコントロール法」が 本の題名で、キリスト紀元第4千世紀の指導的ビジネスエコノミスト の一人のトーマス・R・P・キング(Thomas R.P. King)の著書であった。 この本は我々の銀河系で指導的なロボット製造会社における現代的な コントロール法の使用について述べており、 自由時間にビジネス経済を学んでいるナディネ・M・シュナイダー( Nadine M. Schneider)はあらゆる機会を捕らえてこの分野について学んでいた。 ため息をついて、彼女はホイスラーカンパニーの最も関連した 組織構造が記された章をみていた。この時、後ろのドアが開いて 彼女の上司のハインツ・ヴァルドフ(Heinz Waldoff)が部屋に入ってきた。 彼は何時になくもの思いに沈んで、幾分ショックを受けたようであった。 彼女はそのことを話そうとしたが、すぐに考えを変え、彼がニュー・テイラーの 郊外の一つの道路に面したドアに近づく時、彼の神経質な歩みを追いかける だけにした。 ブルー人の チュツオール・ヴォルク (T鯪z痆 V痆k, Teutzeol Veolk) は部屋の反対側の机の向こう側に座っていて 殆ど関心を示さなかった。彼は上司に話しかけた。 「ハインツ?」 その男は反応しなかったので、ヴォルツは彼に向かって 歩いていった。「全て順調ですか?」 ヴァルドフは横目で彼をちらと見て、入り口のドアの鍵をかけた。 ゆっくりと彼は向き直り、事務所の従業員を数えあげた。 「みんな、私の事務室に来てくれないか?」 他に付け加えることなく、彼は向きを変え事務室に戻った、ドアを 開けたままで。 ナディネはしばらく動かなかった。彼女の目は今閉められた入り口のドアと 開けられたままの事務室のドアの間を行ったり来たりした。そして 同じように午後を持て余すのに忙しい3人の同僚を見た。 誰も口を開かなかったが、互いに見合わせた顔つきは明らかに 驚いていた。ようやくナディネは立ち上がり上司の部屋に入った。 麻痺状態からようやく回復した他のメンバーの先にたって。 「ハインツ?」 ナディネは説明を待ったが、上司は動かなかった。 彼は机の前に集まった4人を無視した。 彼の机に埋め込まれたモニターが起動され、彼の注意かそこに集中してい たからであった。 ナディネは咳払いし、ヴァルドフに話しかけた。 「ハインツ、ここで何か起こっているか教えて頂けないかしら?」 しばらく彼女の命が説明もなしに失われたかのようであったが、 ようやく上司が動いた。 「ああ、わかった。」彼は混乱したまま話し始めた。 そして、真顔になりながら咳払いをした。 「ここに重大な問題がある。」 彼の目は更に何かを求めてモニターに戻った。 「オリンプが攻撃された。正確にはオリンプにあるキャメロットオフィスがだ。」 従業員の顔に当惑が広がった。幾人かは頭を振り、他は視線を下げ、 床を見つめた。共通の関心事は彼らの顔に書いてあった。 「一体誰が?」ナディネはようやくたずねた。「そしてここの私達の 仕事にどんな影響があるのですか?」 「さしあたり何も影響はない。改めて通知が来るまで我々が 最前線にいると言う事と、今から警告レベルを上げるように 命令されたという事以外は。 我々は警戒しなければならない。問題は、何者あるいは何物を監視 すべきかわからないということだ。敵については実際のところ 何もわからない。誰が攻撃しているにせよ、やつらはこっそりと 行動するすべを知っている。 はっきりしているのは一つだけ。敵はキャメロット、そして特に 不死者たちに対して戦いを挑んでいる。 だから、やつらは強力な力を持っているに違いない。 そして彼の視線は再びモニターをさまよった。 「最悪なのは、オリンプの我々の同僚の誰も攻撃を生き延びる事が 出来なかったということだ。彼らはみんな死んでしまった。だから もし我々が攻撃を受けたら何が起こるかわかるだろう。」 「何か良い知らせは無いの?」ナディネは、蒼白の顔でこぶしを固めてたずねた。 「ああ。<タクヴァリオン>が我々を支援し守るためにプロフォスに 向けて発進したそうだ。 サンダル・トークとジョーク・M・カスカルがかなりの大型艦と強力な ロボット部隊をつれて我々の援護のためにここに向かっている。 外回りのエージェント達に現状を伝えて、新たな情報が入るまで 我々の基地は放棄しないと彼らに言ってくれたまえ。 我々が今後数日間隠れて過ごすことは非常に賢明な策だ。 やつらの種族がどのような外見で何処から進化したのか何もわからない。 しかし一つだけ確かなことがある。我々は何処でも何時でも攻撃を 受けるかもしれない。そして攻撃は我々の死を意味するだろう。 今は私を一人にして仕事に戻ってくれたまえ。」 ヴァルドフは同僚達を無視してモニターに向かった。彼らは皆この解散命令に それほどおどろかなかった。時としてぶっきらぼうに見えてもヴァルドフは 望みうる最良の上司だった。彼は部下を100%支援し、従業員の一人たりとも見捨ては しない。しかし、同時に彼はみんなから完全な誓約を期待している。 4人の従業員が部屋を出た後、上司は無線装置にスイッチを入れ、 外回りのエージェントにメッセージを送った。 呼びかけは短く、コードは全員が中央基地に戻る様に署名されていた。 元々このコードはテラ政府が公式にキャメロットに敵対することを決めたという 事態に対して設定されたものであった。 しかし、昨今の混乱と混沌の後、 特にペリー・ローダンが第六使徒に任命された後は、キャメロットに対する 一般的な感情は幾分変化していた。 今や人類は再び他者、特に細胞活性装置保持者を許容し始めたかに見えていた。 少なくともキャメロット組織に取って、特に公的な許容に関する限り、状況は 以前よりずっと好転していた。 ナディネは自分の机に戻ってシントロニクス(syntrone)を起動した。 それはディスクトップモデルで、小型かさばらず、どこにでも持ち運び可能で 彼女が必要な全てをこなすのに足りる性能を持っていた。 彼女はパワーメールを起動した。 これは特殊なキャメロット製のソフトで、数百万ビット長の コードシンボルを生成可能な鍵で符号化した電子メールを 送ることが出来る。 同時にテキストは交換アルゴリズム(transposition algorithm) によって暗号化され意味の無い文字列に変換される。 さもないと、光速より早く動作する高級シントロニクスは 容易にテキストを復号化できるだろう。 地球でのオンライン通信の黎明期には、電子メールは256ビットの鍵で 符号化されていれば安全だと考えられていた。 そのような鍵は古代のコンピューターでは解読に何世紀も要したであろう。 現代のシントロニクスにとってはそのような鍵はたちの悪い冗談以外の 何物ではなく、そのため今では別の方法が用いられている。 しかし、これらの特性はシンロトニクスが気にするものであって、 ナディネはそれらが彼女のデータに行っていることについては ほとんど気にも止めなかった。 しかし、彼女は衛星を通じて、この惑星でまだ活動中の全ての 外回りのエージェントに暗号化されたメッセージを送った。 彼女はソフトウエアを使って公開鍵も添付し、シントロニクスの スイッチを切った。 もの思いに沈んで、彼女は頭に手をやり、彼女の電子メール を受け取るであろう人々のことを考えた。
ウイリアム・V・オルツ(William V. Oltz) は赤道地帯で忙しかった。本部からの警報が届いたとき、彼はカフェに座って 飲み物を注文していた。彼の眉毛には小さな埋め込み機器があり、 今はサングラスと同様の効果を持つダークフィールドを生成していた。 警報が彼に届いたとき、フィールドの一部は更に暗くなり 警報のタイプを示していた。 オルツは殆ど反応できなかった。 彼は、たった今サービスロボットが目の前に置いたお茶に手を延ばし 一口すすった。 そして、彼はフィールドの端に見える小さな文字に視線を向け 眼の焦点を合わせた。 フィールドは瞳の動きを記録した。 人が何処を見ているかだけでなく人の目からどれくらい 離れた所に像が焦点を結んでいるかを探知できた。 この特殊眼鏡に組み込まれたマイクロ工学は、今キャメロットで生存している 最後のシガ人に由来する技術であり、最高機密であった。キャメロットの エージェントだけがそれを常備していた。 オルツはポケットからロケットブック(Rocketbook)を取りだし、 オンライン小説を読むのに忙しいかのように見えた。 特殊眼鏡は彼のメールボックスとの接続を行った。 そうして最新のメールの概要を彼に示した。 微小なプロジェクターが観測者の面前に小型スクリーンに 匹敵するフィールドを作り出した。 このスクリーンは他人には見えず、目の脇からのみはっきりと 見ることができた。 再び、オルツは眼鏡をコントロールするためもう一つの視線を使った。 線の一つは感単符で印が付けられ、強調されていた。 題名は指示だけであった。「ナディネ、返信を請う。」 エージェントのポケットのシントロニクスが秘密鍵を 使って電子メールを解読するのは一瞬で、 すぐに全文がフィールドエージェントの 小型スクリーンに表れた。 彼はメールを読み、そして一気にカップのお茶を空にした。 彼はロケットブックを書類鞄にしまい立ち上がった。 何か特別なことが起こったと気が付いた者は誰もいない。 オルツは断固たる足取りでカフェの近くのグライダーまで歩き、 その内部に座った。 彼は乗り物のエンジンを始動し、彼が好んでいるこの地方の 灼熱の夏の気温にさよならを言った。この後数日は 蒸し暑い事務所に滞在することを強いられるだろう。
彼女はシントロニクスのモニターに表れた名前を数えた。 全部で23人。5人は緑にマークされていた。事務所にいてプロフォスでの オフィスワークに従事している人々。 残りの18人の名前はまだ赤く点滅していたが、彼らが電子メールを開くと 直ちにナディアに事態を伝える自動確認メールが送られる。そして 赤が青に変わり、エージェントの誰が彼女のメッセージを処理したかを 一つ一つ示すことになっていた。 ようやくモニターが変化した。リストの最初の名前が青色にマークされた。 彼女はホルムズ(Holmes)の名前を認めた。その若い女性は今ウインタースポーツ リゾート地に向かう途中で、そこでプロフォスの高名な遺伝学者と 会見することになっていた。 この数分の間に彼女は退路を確保し、数時間後にはきっと本部に 到着するだろう。 更に多くの名前が青色に変わり、 数分の間に殆ど全員が応答した。 しかし、3人の名前は半時間を経過しても赤のままであった。 ヴァルドフにはもう予想がついていた。この3人からの連絡を受け取ることは もやは永久にないことを上司は確信した。
グライダーは 大邸宅(estate?)の 気前の良い前庭に辿り着いた。 ガイネス(Gaynes)は乗り物を彼の前で閉じたままの門の正面に停止させ、しばらく 待った。 邸宅の中では彼の来訪が告げられ、ロボット門番が拡声器を作動させた。 「はい、どうぞ。」 同情のある女性の声が彼に話しかけた。 シントロニクスは訪問者を分析し、男性の感情に最も 良い効果もたらすと計算した音声シーケンスを動作させたのだ。 この方法は訪問者に直ちに満足感を生み出し、 ホストの義務を大幅に簡略化させる。 「私の名前はガイネスです。お待ちになっていたと思います。」 訪問者は短く答えた。 「中にはいって前庭にグライダーを停めて下さい。すぐ、誰かが 側に伺います。」 「どうもありがとう。」ガイネスは乗り物を 門の開いている側に向けながら答えた。 彼は車を停めて降りた。 突然、彼の警報機が緊急事態を告げた。 彼は車に戻ってシントロニクスのチェックをしようとしたが できなかった。 エネルギー弾が家の窓の一つから発射され、僅かのところで 彼をそれた。 エージェントはすぐに大地に伏せグライダーの背後に隠れるために 転がった。 同時に彼の手は上着の中に滑り込み小型携行兵器の取っ手の周りで 閉じた。ジョニー(Jonny)はエネルギーを 致死ビームに高めるまで制御レベルを変えた。 そして彼は防火壁の反対側まで転がりすぐに窓を撃った。 しかし、もう空っぽであった。 速やかに彼は状況を判断し、窓の一つの背後の敵の位置を 見極めようとした。目では何も分からないので、彼はもう一度グライダー の可動シントロニクスの元に戻ろうとした。 ドアが開いたとき、新たな一撃が彼を狙って発せられた。 今回は彼は直ちに反応しドア枠に寄りかかって立っている 姿に発砲した。 残念ながら狙いは外れ、彼は敵の再度の射撃を引き起こさない様に グライダーを離れて邸宅の壁に向かって走った。 走っている間に武器をベルトに差し、彼は邸宅の外壁に飛び上がり バルコニーの下の端に辿り着いた。彼は自分の身体を持ち上げた。 最後には手すりに身体を横たえ、反対側の床に落ちた。さっと見渡して 誰も辺りに居ないことに彼は気が付いた。 再び彼は武器をつかみ、誰が彼を狙撃できたのかをしばし 考えた。元々、彼は テラナーの政策に最近大いに不満を示し、キャメロット人よりの 政策を要求しているある女性政治家と会見の約束をしていた。 プロフォスではペリー・ローダンを第六使徒と認め、彼がギャラクティカム( Galacticum)で始動的立場に戻ることを期待する勢力が次第に力を 持っていきつつあった。 第六使徒が本質的には銀河の消防団であって、この希望は用意には実現しない とは言え、その背後の基本的考えは指示されねばならない。 そして、それこそキャメロットが彼女との接触を望んだ 理由であった。 彼女に何が起こったのか?誰が彼を撃ったのか?今こそ明らかにしなければ。 ガイネスはポケットに手を入れ、Tバード(T-Bird)と呼ばれる装置を 取り出した。それは一種のスキャナーで建物の壁の背後を見ることができる。 それのスイッチを入れた時m始めは何のイメージも表れなかった。 しかしその後彼は何かをつかんだ。 バルコニーのドアの背後の部屋は寝室で,ベッドの上に若い女性の 裸体を彼は認めた。 ジョアンナ・ペレス(Joanna Perez)、彼が元々会見しようとしていた 政治家だ。彼女は身動きしていなかった。 装置は再びエージェントのポケットに消え,彼は短時間で あらゆる可能なコードシグナルを発見、模擬できる別の装置を探った。 彼はそれをドアの鍵の上に短時間置いた。 ドアが開いたとき彼は武器を部屋の中に向けた。 しかし、動くものは何もなかった。 ゆっくりと彼はベッドに向かって歩いた。彼はその女性の 脈を測ったが、脈は無かった。 彼女は死んでいた。 彼は彼女を横たえたままドアに向かって歩いた。 ためらいながらドアの枠に向かって歩いた。ドアを開けるセンサーの 動作エリアに入る前に彼は再びTバードのスイッチを入れた。 スクリーンには何も写らなかった。 決然として彼は歩を進めドアの開閉装置を動かした。 ドアは脇に移動し、彼を直に狙っている武器が見えた。 その武器を持っている男は仮面をつけていた。 ゆっくりとブラスター(blaster)を床に置き、彼は両手を頭の上に挙げた。 なぜTバードが働かなかったのか?彼は自問した。 「さあ、お望みは何だ?」彼はたずねた。死が間近に迫っていると 理解していたが、彼は恐れなかった。 やつらは彼を撃ち殺そうとしていた。それならなぜ今になって彼と 話そうとしているのか? 彼も会話を強いる積もりはなく、敵の注意を逸らしたいだけであった。 その時、彼は自ら崩れ落ち開いたドアを通って転がり出た。 彼の身体はもう一人の男にぶつかり押し倒した。この必死の 攻撃は成功するはずであった。不幸にも彼はTバードのスクリーン上に 別の男を認めておらず、この男は今ゆっくりと武器を持ち上げた。 一言も発せずに彼は撃った。 目の隅でガイネスはその男が武器を持ち上げるのを見た。 パニックに襲われ、彼は傍らに転がろうとした。 しかし、別の敵が彼の真上から倒れこんできたのでガイネスは 身をかわすことが出来なかった。しかし、彼の敵もそうであった。 スローモーションの様にガイネスは光線が敵の頭を貫くのを認めた。 光線は減速すること無く彼の目に真っすぐ向かった。 目は頭の残りと同じくらい早く燃え上がったが、 何かを感じるにはおそすぎた。エージェントは警報を確かめる前に死に、 彼は他の2人のエージェントが彼と運命を伴にしたことを知らなかった。 プロフォス上のキャメロット人に対するモードレットの攻撃が始まった。
ヴ ァルドフは指でテーブルを叩いた。彼は一種の行進曲のリズムを保って 何度も繰り返した。 タタターン、タタターン、タタターン。それは止むことなく、 上司がいかに感情的にそして神経質になっているかをナディネと 他の者達に示していた。 彼女も感情が動揺していた。 彼女は3人のエージェント全てを知っていて、 キャメロット人は全て特別な繋がりを共有していた。 全銀河の殆どを敵とみなす小さな血族に属するもの達のみか 共有できる繋がりを。 間違いなく、そのことを公言できる人は余りいない。 ナディネは失った友人達を思って声もなく悲しんでいた。 しかし、その一方で彼女の上司は指で叩くことにより 彼女の神経をいらいらさせ始めた。しばらく彼女は視線を まだ同じリズムで打っている彼の指に向けた。 タタターン、タタターン、タタターン。 そして、彼が正面のモニターを腹だたしげに 眺めた時、彼女は回復し彼の目を再び見た。 スクリーン上に並んだ数字は<タクヴァリオン>がまだどのくらい 遠くに居るかを示していた。 あと数時間で船はプロフォスの周りの周回起動に入るだろう。 その間に惑星政府には通知され、政府は支持を表明した。 彼らは<タクヴァリオン>乗員が地表に降りることを了承したが 巨船は軌道上にどどまるように念を押した。 このことは戦闘コマンドの乗った救命艇だけが惑星に降り立つことを 意味する。この男女たちが残りのエージェント達を探し 全員を本部に集結させることになろう。そして彼らはプロフォスを 離れることになる。 しかし、このためにはまだ何時間もかかるだろうし、 その間にも多くのことが起こるかもしれない。 エージェントの一人はキャメロット人の本部まで辿り着いた。 今、キャメロット人は6人いて、より多くの人が到着するのを 今か今かと待っていた。しかし彼らは何処にいるのだ? 待機中、彼は一種の無線所在システムをインストールした。これは 任意の時刻での全てのエージェントの位置を表示できる。これは敵にとっても 事態を容易にするが、3人の犠牲者がこれほど早くでたからには 敵が全てのエージェントの所在を知っているという仮定から 出発しなければならない。 そのため、彼らは集結のリスクをおかすことにした。スピードが 大事だ。 そして、ヴァルドフは部下の何人かが死んだかどうかは少なくとも知っていた。 たった12人が生き残っている。 まさにその瞬間、電子マップのドットの一つが消えた。 指は、電源が切られたかのように叩くのを止め、そしてずっとヒステリックに 再開した。 ナディネはぎゅっと閉じ、目の縁から溢れ出ようとする涙を 押さえ付けた。 トーマス・R・ジェファーソン・メイヤー、キャメロットで 訓練を受けた中で最も優秀なエージェントの一人。 今や彼は死んだに違いない。100%確実とは誰にも言えないが。 時間との競争が始まった。<タクヴァリオン>は今何処に?
「あとどれくらいだ?」司令は低く言った。 彼は我知らずのうちに ヴァルドフの青写真(訳注:日本語なら「影法師」の方が意味が通る?) となっていた。なぜなら、彼もまた 椅子のひじかけの上を叩いていたから。 「1時間です。」コンは答えた。彼女は、目的地にできるだけ早く 着くためにエンジンを絞り上げている操縦士の直後に立っていた。 惑星は既にスクリーン上に姿を現していた。 ゆっくりと、殆ど耐え難いペースで大きく大きくなり、 ついには大気を持った地球型惑星の特徴を示す様になった。 白い斑点のある青い球体、それは印象的な様子を見せ始めていた。 カスカルは航宙科学の美に目もくれなかった。 その瞬間、彼は心密かに全く異なったものを 感じていた。時間がムダに過ぎるのを望まなかったので 彼は座席から通信回路を開いた。肘掛けのマイクロホンフィールドが 歩兵戦闘小隊の一つを最高警戒体制に置くという 彼の声を記録した。 そのグループは100名の屈強な男たちから構成され、 全速力で1隻の救命艇に駆け寄った。 キャメロットのエージェントがまだ見つかりそうな全ての場所に 戦闘部隊を降下させるのが計画であった。そして、戦士達は エージェント達を探し、守り、救命艇が回収するまで待つことになろう。 不幸にも惑星政府はそれほど協力的ではなかった。 キャメロット人は、プロフォスの第一テラナー(訳注:政府主席のことか?) が表明した様に、 自分たちの「内政問題」は自分たちだけで対処すべきであると彼らは 主張した。 彼はエージェント達の支持を拒否した。 彼はキャメロット人の問題を喜んでいる様にすら見えた。 彼自身の惑星でしばらくの間トラブルを引き起こしていた 連中の問題を。 そして、結局のところ、彼はかなりの数の優秀な科学者を この組織に引き抜かれて失っているのだ。 こんなわけで、僅か1隻の救命艇が着陸を許可されたのみであった。 そして、キャメロット人は秘密裏に行動することを許されたが、 これは時間を浪費する結果にもなった。 そして、このためエージェント達を同時に救出することは 出来ず、一人、また一人と保護し、最終的に解放されねば ならなかった。 何れにせよ、事態は複雑化しており、 カスカルはその中でベストを尽くすのみであった。 ようやく宇宙船はプロフォスの周回軌道に入った。 カスカルは席を空け、第一士官の コリーネ・コンに話しかけた。 「指揮を引き継いでくれ。」彼は命令し、 既に武器に手を延ばし、矢筒を持ち上げたトークに向かって頷いた。 そして、彼らは駆け出し、司令室を出て、救命艇格納庫への 最短ルートを目指した。 コンが<タクヴァリオン>が周回軌道に入ったとアナウンスをした時に 丁度彼らは救命艇に乗り込んだ。 「直ちに発進だ。」指揮官はパイロットを指差して叫んだ。 「すでに飛行中です。」若い男が目を輝かせて返答した。 彼は格納庫のドアが完全に開くまで待てなかったのだ。 彼は上陸艇をショックフィールドの上に滑空させ、十分な余地が できるないなや絞り弁を叩いた。船は半分開いたロックに向かって 下方にジャンプし、何処も接触すること無く、両方に数メーターのすき間を 残して通過した。 救命艇は直径30メートルであったが、パイロットは剃刀の歯の精度で 何も見落とすこと無く行動した。 その上、彼は紅潮して操縦幹を握っていたわけではないので、 カスカルはこの危険な演習について何も言わなかった。 彼は脇目でトークを見た。彼は面白がってにやりと笑い カスカルの視線に頷き返した。 彼の目は喜びに輝いていた。そして彼はスクリーンに 視線を戻した。 「最初の目標は本部だ。安全確保と占有をしたらエージェント達の ポジションに飛ぶ。 別動隊は各チームの脱出が迅速かつ正確に行われるように準備する。 一瞬一瞬が命にかかわる。すでに4人のエージェントを失った。 たった一人でも多すぎると言うのに。 では諸君、仕事にかかろう。」 カスカルは命令をどなり、武器に手を伸ばした。 彼は武器の全てが手筈通りになっていることを、 これまで100回もこなしてきたのと同様に 確認し、磁気ホルスターに戻した。 彼とトークは第一グループに加わる。それは 15名の屈強な男たちからなり、全てのグループ中で最大人数であった。 その任務は救命艇が彼らを回収に戻るまで本部を守ること。 願わくば、その時には全てのエージェントが艇に乗っているように。 パイロットは20分で本部に着くとアナウンスした。 時間はゆっくりと経過し、ようやく主ロックが開いた。 パイロットが艇を離れるように命じた数秒すらためらわなかった。 グループの戦闘に立ち、彼はロックの外に飛び出し、 自由落下状態に入った。400メートル下には航空写真から 知っている通りを認めた。 キャメロット人のオフィスがある通りだ。 近くの家は全て空で、キャメロットのメンバーを除いて 皆避難していた。このメンバーこそ彼らが救助しようと やってきた目標だ。 すぐ後ろにトークをさらにその背後に15名の男たちを 従え、真珠の首飾りの様に空を降下していった。 彼らが通りに到着し、正しいビルと判断したオフィスに 向かって走った時も隊列は乱れていなかった。 ドアは開いていて、第一グループが目的地に到着した。
ドアが開いて<タクヴァリオン>の戦闘部隊が入ってきたとき、 全てはまだ日常的であった。 しかしドアが閉じた後多くの事が変化した。 もちろん彼女は人生が驚きに満ちていることを知っていた。彼女はまだ 非常に若いが、既に多くの驚きを体験してきた。 例えば、彼女はキャメロットに加わるなど考えても見なかった。 もし、彼女の父がまだ生きていたら、彼女がキャメロットに参加することについて 何を言ったか彼女には分からない。特に彼の死が彼女がこの組織に参加する 元々のきっかけになることを知っていたとしたら。 それから多くのことが起こった。 彼女は僅か数カ月後には母を失った。しかし、死によってではない。 彼女は拉致されたのだ。誰がによってかは誰も知らない。 何処に連れさられたのかも分からない。 ここ数年は彼女はママについて何も耳にしていない。 これが彼女がキャメロットに加わった理由の一部であった。 彼女はこの組織の助けで母親の消息を見つけたいと願っていた。 しかし、過去数年来の出来事の後では、彼らはあえてその労 をとろうとは決してしなかった。 そして今、彼が彼女の正面に立っている。 戦闘服の下では筋肉がはち切れるばかりであった。 彼はやせて長身で、やり手の印象を与えていた。 ライトグレイの目は知性と勇気のみならず、 かなりの優しさも示していた。 おそらく彼が女性の前に立つときは殆どそうなのだろう。 例え彼自身が自覚していないとしても。 彼が話しかけた時には彼女は既に恋に陥っていた。 「ハロー、私はジョーク・M・カスカル、<タクヴァリオン>の司令だ。 状況はどうなっている?」 「ナディネ・・・。」彼女はささやき、そして彼女は我に返り、 咳払いして最初から話し始めた。彼の唇を飾るほほ笑みは、しばし彼女を いらいらさせた。なぜなら、それは公然と恩着せがましい様子であったから。 「ナディネ・シュナイダーです。状況は変わりありません。」彼女は きっぱりした口調で言った。そして向きを変えた。「ついてきて下さい。 上司の所にお連れします。」 彼女の声はしばらくの間、きっぱりした調子であったばかりではなく、 彼女は無関心を装う冷静さの感じを加えようとしていた。 しかし、カスカルは彼女の目を見、彼は無関心ではなかった。 再び彼の唇が動き、今度は ナディネにも気に入るであろうほほ笑みを示した。 彼女が背後のオフィスに向かう戸張で彼に振り向いたとき、 彼の顔は再び無関心さを保った。 彼は頭一つ分小さなやせた女性に続きながら、視線は 彼女の身体を感嘆してさまよった。 もちろん、状況は危険極まりないが、彼はそれを楽しんだ。 重要なことに対する彼の見解を失うことは、あらゆる危険にもかかわらず ずっと重要なのだ。 そして、時空の歪みで費やした年月の間でさえ、女性に対する 彼の本能は眠らなかった。 そして、この女性は一級品だ、彼ははっきりとそう感じた。 彼女の傍らを通り過ぎたとき、彼は極近くまで接近した。 彼は彼女の香りを吸い込み深呼吸した。 オフィスに入ったとき、彼はしばし軽いめまいを感じた。 なんて女性だ、彼女が彼の後から部屋に入ったとき、彼は思った。 「上司のハインツ・ヴァルドフです。」彼女は言った。
コケは、彼が森を走り抜けている間に 彼の足跡を湿らせていた。辺りは暗いが、夜の闇の中で彼の位置を 突き止めることのできる赤外線探知機を敵が持っているのは 殆ど自明であった。 彼もまたそのような赤外線探知機を身につけていたが、2〜3の影しか認めることが 出来なかった。 装置が故障しているのか、彼が本当は追跡されていないのか。 しかし彼はこのリスクをおかそうとは思わなかった。 彼は正面の小川の周りを迂回しようとしたが、可能性はなかった。 それ以上時間をムダにすること無く、彼は真っすぐに小川を突っ切って走った。 足を濡らして、彼は反対側まで横切った。 それから彼は小川を後にし走り続けた。濡れた足は地面に 水滴を撒き散らし、暗やみでもはっきり聞こえる騒音をたてた。 他方、そんなことは大した違いではない。なぜなら、やつらは 彼が何処にいるかを、ハンティング技術のおかげで 正確に知っているから。 彼は何より自分自身に腹をたてていた。もし、周りにもう一寸 注意を払っていたら、やつらが直ぐそこに迫っていることに 気が付いたはずだから。 しかし、その時は気が付かず、今となってはそれを悔やんでも 遅すぎる。 他方、考えるのに遅すぎることはない。 潜在的な敵を知らせるはずの装置は反応しなかった。 これらの装置はキャメロットで作られ、キャメロットスパイ産業の 最新製品であった。 それは、この銀河で発見されうるあらゆるものを可視化するはずであった。 天の河の他の権力グループはTバードを無力化できる技術は持っていない。 それなら、誰が?やつらは未知の敵と出会ったのか? モードレッドは別の銀河から来たのか?彼はナディネのメールから この組織について教えられていた。 メール自体は危機の短い概要であったが、警報の理由を 説明していた。 彼の考えは、エネルギー光線が傍らを居抜き、1本の木の幹に容易に穴を あけた時に中断された。その木はまだ立ったままであるが、今や穴が開いていた。 トムは身体を傾け、木の背後に駆け込み、それから別の植物の周りを疾走した。 しかし、直後に彼の道は塞がれた。 彼の真正面で数本の倒れた樹木が道を塞ぎ、迂回する道は無かった。 樹木を飛び越えようとブースターのスイッチを入れようとした 丁度その時、数人の人影が樹木の山の上に立ち武器で彼を威嚇した。 彼は振り返ったが、この連中の仲間が彼のほうにやってくるのを 見ただけだった。 もはやこれまでか、が彼の最初の考えで、武器を 握りしめた。 今までやつらは一度も捕虜を作っていない。 彼に対して態度を変えるようなわけが無い。 唸り声が大気を満たし、エージェントは騒音が 惑星大気圏を高速で移動している飛行物体のものであると 見極めた。 その物体は樹木の上を飛び越え、その後高速で飛びさった。 敵はほんの一瞬だけ注意を逸らしただけであった。 やつらはエージェント以外の誰にも見られたくないのは 明らかだったが、それ以上の危険は無いようなので、 最後を待つしかない男に近付き続けた。 少なくとも、狩りは終わったかのように全てが見えた。 トム・ジョーンズは頭上の飛行に続く騒音のいくつかを 容易に聞き分けた。それは物体なり人なりが大気中を自由落下して、 樹木の頂きを通って音をならしているかのようであった。 敵はだれ一人この騒音を聞いていないようであった。 彼らは、武器を手に辺りを見渡しているおそらく無防備な生贄に ゆっくり接近し続けた。 連中の一人の背後に今、彼はそれまでに無かった人影を見た。 その人影は敵を排除しようとした。しかし、彼がそのようにしているのに、 敵は全く音をたてなかった。全てが不気味なほど無音であった。 次第に神秘的な攻撃者たちが、それほど神秘的でない防衛者の犠牲になり、 エージェントは彼を威嚇する敵が次第に減っていく様を うっとりと観察した。 最後の3名の敵が危険に気が付いた時、彼らは状況にけりをつけるため 彼に武器を向けた。彼はその一人を撃ち、他の二人は未知の同盟者たち が引き受けた。 「ジョーンスか?」男たちの一人がたずねた。 「はい。」とエージェントは答えた。 「こちらへ、 我々は再回収されるまであんたを解放し保護する命令を受けている。 やつらの仲間が他にも森の中をうろうろしていないことを望むね。」 その男は彼を自分たちの真ん中に引き寄せた。半時間もせずに彼らは森を 後にした。ゆっくりと彼らは最寄りの都市の一つまで歩を進めた。 彼らは自分たちを回収するはずの救命艇を待った。けれども、彼らは 長い待機を強いられた。
彼女は、彼が上司と向かい合って椅子に座って 最新の情報を聞いていたとき、その大きな背中に見入っていた。 上陸チームからのニュースは入り続けた。いくつかは成功の報告であったが、 チームの2つは失敗であった。彼らが到着した時には目標の人物の死亡を 確認しただけであった。 彼女の友人達が死んだ、そしてそのことが 彼女をゆっくり現実に引き戻した。 赤いライトのもう一つが消えた時、彼女の目に涙があらわれ、彼女は部屋を出た。 自分のシントロニクスに戻ってたった今死んだのが ウイリアム・V・オルツであることを彼女は発見した。 帰還できなかった者がまた一人。 パワーメールは一時停止されたが、彼女はメールボックスの小さな旗を 見たとき、旗は立ち上がりメールボックスが赤く点滅し始めた。 緊急メッセージ。 無論のこと、この状況では彼女の元に来るものは全て重要である。 もしメールの作成者が彼女が重要なメッセージだけを受信し、 特に重要なメッセージを正しく伝えようとするなら、 特別なシグニチャだけが意味をなす。 彼女はメールを開き、オルツのシンボルを認めた。 素早く彼女は今読んだメッセージと受け取ったメールを 比較した。彼のシンボルは消えており、 一体どのようにして彼はメールを送ることが 出来たのか? シントロニクスは自動的にメールの送信元を探知し、 オフィスにかなり近い地域の詳細地図を 表示した。 エージェントは森の中僅か数百メートルの所に居る。 直ぐ近く、同時に到達できないほど遠くに。 なぜなら、彼が書いているメールによれば、 彼は銃撃で致命的な怪我をおい、動くことが出来ないから。 ナディネは飛び上がり、部屋の中に向かってこのメッセージを 叫んだ。 ブルー人の チュツオール・ヴォルクが最初に反応した。 彼はそのメッセージを上司に手渡した。 カスカルはメッセージを見るために部屋を離れ、4名のチームを 派遣することに決めた。 ナディネは<タクヴァリオン>の司令官がすむまで待っていなかった。 普通なら彼女は暮れつつある夜に一人で飛び出して、 キャメロットの敵にまた一つ標的を差し出すような真似は 決してしない。 しかし、彼女の感情と一般状況の混乱のため彼女の自己制御の 限界に近づいていたため、彼女はオフィスを一目散に飛び出した。 中にいた男たちの誰も彼女を止めようとはしなかった。 「ここに留まれ。」カスカルはトークに叫んだ。 テラナーは目を丸くし何かをつぶやいた。 それは女性の愚かさについての古代の呪いの様に 怪しげに聞こえた。そして彼は彼女の後を走り出した。 ヴォルクが彼の直ぐ後についた。兵士の二人も 走りに加わった。 トークは他のものを引き戻し弓に手を延ばした。 「持ち場に戻って。」彼は叫んだ。そして、彼は上司と話しする為に引き返した。 「いったい何が起こっているのか?」 上司は机の背後から飛び上がったが、部屋を離れなかった。その代わり、 彼は電子地図を見守った。 今、それは全てのエージェントが死んだか戦闘コマンドに救助されたかを 示していた。 「おそらく死んだ連中の一人がメッセージをおくったんでしょう。」 蛮人は言った。 「しかし、罠だと思います。 結局のところ、誰だってメールを送ることが出来ます。特に連中が 敵のシントロニクスを持っていれば。彼を発見することは期待できません。 むしろ、我々の部隊の幾つがそれを回収するか見積もらねばなりません。 第一テラナーとの緊急回線を要求します。」 ヴァルドフはうなづいて回線を開いた。トークはテラナーと議論し <タクヴァリオン>からより多くの援助が得られるように主張した。 プロフォスの第一テラナーは要求を拒否したが、地元警察部隊の 援助を申し出た。彼らは直ちに行動する様に配置されるだろう。 トークは同意した。 彼は上司シェフ(Chefs?)の小さなオフィスを出て窓際に席をとった。 彼は自分の目で闇を見透かそうとしたが、暗闇中では何者も認めるのは 殆ど不可能であった。 赤外線眼鏡を身につけた時、暗闇に何かを見分けることが 出来たが、彼の目に入るものは道の反対側の建物の背後に伸びる 樹木だけであった。 何も見えない、そして何も聞こえない。 警察部隊はまだ遥かかなただ。カスカルは何処に、そして あの女性は何処に?
彼女は何の問題もなく道路の反対側に辿り着き庭を 走り抜けた。カスカルは殆ど彼女に追いつきかけたが、森に着くまで 彼女をとらえることが出来なかった。 突然、1本のエネルギー光線が一瞬黄昏に浮かび上がったとき、 彼らは最初の樹木の影に一緒に倒れこんだ。 ナディネは彼女らが明確な標的になっていると言う事実をよくわきませていた。 なぜなら、彼女らはまだ森の外に立っており、 彼女ら自身は暗い森の内部が何も見えないのに 彼女らはまだ僅かに明るい空を背景にしてずっとはっきり見えるから。 建物から飛び出した時には慌ただしく行動したのと同じくらいに 今度は彼女は用心深く行動した 彼女は武器を磁気ホルスターから引き抜き、森の端をそれで撫で払った。 そして、いくつかの茂みの背後に姿を消し、闇に溶け込んだ。 彼女からさほど離れていないところでカスカルもまた遮蔽物を見つけ、 ヴォルクと兵士達が同様に遮蔽物に辿り着いたのを 殆ど気にもとめなかった。 枝の下にうずくまったまま、若い女性の方に這っていった。 そのやせた身体は赤外線眼鏡のおかげではっきりと見えた。 彼は敵が同様の装置を持っているに違いないと今になって悟り、 若い女性の隣に横たわったとき、戦闘服の防御バリアのスイッチを 入れた。 彼女も戦闘服を着用していたが、この軽量セットは危険なほど 弱い防御バリアしかなく、彼は彼女を自身のバリアに取り込んだ。 彼女の細い指はシントロニクスのキーボードの上を走り回り、 彼女は拡大図の結果を小型スクリーンに写した。 「そこ、正面、約300メートル。そこに彼が居るはず。」 「もし彼が本当に生きているとしても、 これが罠だと考えないのかい? やつらが彼のシントロニクスを手にいれたら、やつらだって 君にメールを送れるだろう。やつらは彼のプログラムを 動かすだけで良いのだから何の問題もないだろう。」 「いいえ。」彼女はきっぱりと言った。 「私はオルツを良く知っているわ。彼の書体を知っている。それに、 もしオルツが殺されたのなら、シントロニクスは自己破壊されているわ。 あの男はとても用心深いの。彼は私達の技術を敵の手に渡すような ことはしないわ。」彼女はきっぱりと見つめ、彼も 彼女が思った通りの性格(format?)であることを認めねば ならなかった。 「そうは言っても、あんな風に走り出すべきではなかった。 おそらく、やつらは我々をおびき寄せることが出来るように 彼を生かしていて、現実に我々はまた問題を抱え込むと言うわけだ。 ここにいるより本部に留まる方が君はずっと安全だったのに。」 「この銀河系にはもう何処にも安全な場所は無いわ。 貴方の側にいるほうが安全と思うの。」 一瞬、彼女の目は少し前までの堅い輝きを失い、カスカルは その背後に恋人を認めた。 両親とはぐれ今日まで見つけることのできない女性、 友人を必要とし、彼、カスカルにこの友人を見つけた女性。 テラナーは咳払いをして頭を振った。 「まだここに解決すべき問題がある。」彼は 明らかに傍らの美しい女性に心を奪われないように務めながら、 彼女を促した。 「いくぞ。」彼は言ってゆっくりと彼女が示した方向に 進み始めた。 彼らの背後で何かが爆発し、カスカルは素早く振り向いた。 キャメロット組織のオフィスの正面で爆弾が爆発し、 一群の男たちが建物を攻撃していた。 もう一つの罠、が彼の最初の考えであったが、直に彼は 全ての雑念を忘れた。 傍らにブルー人、プロフォス女性、そして二人の 兵士を引き連れて彼は薮林をはっていった。 匍匐前進はいかなる攻撃からも彼らの身体を守ってくれないことを 十二分に知りながら。
最初の攻撃者が暗闇から表れた時、 トークは赤外線眼鏡で直ちにその姿を捕らえた。 彼は弓をつかみ、矢筒から矢を1本取り出した。 その頂部の赤い警告色はそれが爆薬で満たされていることを示していた。 一振りで衝撃点火器のスイッチを入れた。 彼はその矢を弦にかけ合成弓を殆ど苦もなく肩まで引き絞った。 彼はその矢を攻撃者の正面の地面に向けて放ち、 衝撃点火器は爆発を引き起こした。 彼らの身体のいくつかが空中に舞ったが、殆どは何事も 無かったかのようにオフィスの建物に向かって進み続けた。 周りの建物では動きは無く、そこの住民は何時間も前に 避難していた。幸いにも、 オフィスは郊外に位置しているばかりではなく、 中心部からはずっと離れていた。そのため、 今日、初めてこの辺りに官憲があらわれた時、 それほど多くの人々が立ち退く必要は無かった。 すぐに官憲は再び現れるだろう、しかし、今のところ 防衛者たちはまだ孤立していた。 「救命艇は何処だ?」彼はマイクに怒鳴った。 返事を待ちながら彼は冷静に次の矢をつがえた。今度は非爆発性のものであった。 彼は敵の一人に慎重に狙いをつけ、矢を飛ばした。 その一撃は目標を居抜いた。矢は倒れた男ののどを貫通して、彼の身体は しばらくのたうち回っていた。 しかし、エクソタ・アルファから来た男は結果に気を取られなかった。 メスを持った外科医の様に、切り取られた組織に注意は払わなかった。 「12のコマンド部隊を降ろしました。そのうち4部隊が戻って同乗しています。 出来るだけ早くそちらに向かいます。ところで、たった1名の生存者しかいません。 他はみな待ち伏せされて撃たれていました。」 ひどい状況だ、トークは思った。 もし、事態がこんな風に続くなら、 彼らは、キャメロット人のたった一人を守るという問題はおろか、 彼ら自身の命を守るという問題にも直面することになろう。 再び彼は弓に矢をつがえ、もう一人の攻撃者を撃った。 彼の回りではエネルギー光線が攻撃者の方向に撃たれたが、 攻撃者は尽きること無く現れるかのようであった。 やつらは森のどこかに基地を持っているに違いない。 カスカルが4人の戦士と姿を消した森に。 ためらいがちに蛮人は弓を下げたが、すぐに再び射始めた。 そのグループに対して出来る最良のサポートは戦い続けることだ。 彼らはまだ好成果を得ていないのかも・・・。 彼女はテラナーの直ぐ後ろに付いていた。 彼はその間に彼女が示した場所に到着した。 彼らはほんの数歩先にエージェントの死体を発見した。 簡単な検査で彼が数分前まで実際にまだ生きていたことが示された。 しかし、胸の穴はその時には既に彼が精神錯乱に近い状態で あったことを明確に示していた。あの電子メールは 彼の最後の生命の印であったのだ。 若い女性は何も言わなかったが、彼女の顔が全てを語っていた。 彼女は悲しい、しかし彼女はそれを見せたくはなかった。 同時に、彼女は大きな間違いをしたことを認める強い気持ち も持ち合わせていた。 カスカルは振り返り、戻って他のみんなを助けようという意味の 身振りをした。 ゆっくりと彼らは来た道を戻っていったが、一瞬の内に敵と 遭遇した。カスカルは最後の瞬間に撃つことが出来た。 敵は音もなく大地に倒れた。しかし彼らの周りで沸き起こった 混乱の中では騒音と言えども聞き取ることは殆ど出来ないだろう。 彼らが次の避難所に辿り着くまでに長くはかからなかった。 そこからはキャメロット本部の全景(overview)を 良く見ることができた。 攻撃者は大グループで攻めたて、建物に圧力を加えていた。 カスカルは無線のスイッチを入れ、トークに状況を伝えた。 彼は蛮人から多くのことを知らされた。次いで彼は救命艇を呼んだ。 まだ回収するグループが3つあり、その後戻るとパイロットは言った。 約15分。少なくとも本部の外にいる人々に取っては長すぎる。 船が戻ってくるずっと前に発見され殺されているかもしれない。 最初の襲撃者が彼らに向かって来たとき、若い女性は 撃ち始めた。カスカルは自分が撃つ直前に彼女を観察した。 彼女の射撃は正確で計算されたものであった。 明らかにその女性は良い訓練を楽しんでいた。 彼がこのことを彼女に話したとき、 一撃が彼の防御バリアをたたいたまさにその瞬間で あるにもかかわらず、彼女の目が楽しげに上がる様を 見落とさなかった。 しかし、彼女の防御バリアをこじあけ、完全に破壊した一撃は 彼の目をくらました。すぐに彼は彼女の正面に飛び、 自分の防御バリアで彼女を覆った。 彼女は崩れ落ち、彼はつかまえた。 二人の兵士が防御を引き受け、その間、カスカルは 若い女性を背後にかくまった。 彼女はしばし意識を失った。 彼女は引き寄せられ、テラナーの腕に 横たえられた。 この一撃が彼女の身体に与えた損傷を見るとタフな戦士も 深い苦悩を感じていた。 戦闘服が胸の直ぐ下で完全に燃え尽きていただけでなく、 身体も重大な損傷を受けていた。 傷の境界ははっきりしていたが、 彼女の腸の大部分は燃えつきていた。 これは間違いなく苦痛であろうが、おそらく ショックによって彼女は痛みを殆ど感じて いないのっだろう。 痛みが戻ってくる前に、彼は彼女に鎮痛剤を与え、彼女の身体に 移動用医療シントロニクス(medosyn)を取り付けた。 どんよりとした目でディスプレイを表示させた。それは絶望を煽り立てていた。 <タクヴァリオン>船上で速やかな治療を行えば間違いなく彼女は助かる けれども、船は救命艇と同じくらい遠くにあった。 薬は効き目をあらわし、テラナーは彼女の身体ごしに片手で 攻撃者に狙いをつけた。その間彼は両腕で彼女を守っていた。 腹だたしく、彼は敵が動かなくなるまでトリガーを引き絞り 続けた。 「ナディネ、死んではいけない。気をしっかり持って、部下はすぐやってくる。 彼らは我々を救い出し、君は生き延びるんだ・・・。」 彼女が殆ど死にかけているということを悟った時、 悲嘆とちくちくする痛みが確かに彼をとらえた。 彼女を救えたかもしれない時間は過ぎ去ってしまったのかもしれない。 例え今救命艇が来ても、彼女はこの傷を生き延びることは出来ないだろう。 戦闘は船が彼らの頭上に現れるまで続いた。 予告された警察部隊の姿が全く見えないうちに、救命艇は キャメロット本部に到着した。 無愛想な苦々しさをもってカスカルは心の中で それほど好意的では無かった執政官に感謝の手紙を書いた。 救命艇が砲火を開くと、抵抗は直ちにやんだ。 船は着陸しオフィスのドアが開いた。 負傷した男たちが外に運ばれ、トークが一行を 船に案内した。 ヴォルクと二人の兵士達が最初に傾斜路に入り、残りのキャメロット人が 続いた。 トークは傾斜路の上でナディネを腕に抱えた カスカルの前に立った。 彼らが船の内部にはいるやいなや ロックは閉められ、救命艇は安全に向かって加速したときには 傾斜路は船に引き戻されていた。 残念ながら、危険は過ぎ去ったわけではなかった。
合成弓 は、船上では役に立たないので、部屋の隅に立てかけられた。 トークは火器管制盤の正面にあいていた椅子に滑り込み、 標的の座標を示して砲手を助けた。 こんな風に彼らは良いリズムを紡ぎ出した。また、それが良いことでもあった。 なぜなら、探知機が突然彼らの救命艇を目指す多数の宇宙船を報告したから。 それは1000メートル級の球形船の小艦隊であった。身分証明もなかった。 彼らが度の権力グループに属しているのか、そして何処からきたのかを 示すことは出来なかった。 トークは艦隊が天の河から来たことを疑った。 攻撃者達は皆そこから転送機で来たことは疑いない。 だからこそ、事実上無尽蔵の部隊を送り込むことが可能だったのだ。 彼は肩ごしにカスカルが若い女性を椅子に寝かせる様を見た。 彼女の顔はリンネルの様に真っ白で、傷を見るだけで 全てが分かった。 カスカルは彼女の髪を額から脇に整えた。 おそらくもうしばらくは司令官なしでやらねばならないので、 トークは<タクヴァリオン>に救命艇が飛び込むことを可能にする 座標を伝えた。 少しづつ彼らはランデブー点に近づいた。 それはひどく呪われていた。 防御バリアはまだ第一撃を吸収できた。 エネルギービームはバリアに当り、それをずっと明るく輝かせた。 小型宇宙船が巨大な火球と変わるまで幾らもかからないだろう。 実際にはもっと時間がかかるとしても・・・。 しかし、ようやく彼らは正面に格納庫の一つへの入り口を見た。 救命艇は格納庫に飛び込み、扉が彼らの直ぐ後ろで閉じた。 <タクヴァリオン>のエンジンは軌道から、そして それほど多くのキャメロット人が命を落とすのを目撃した惑星から 船を引き離した。 トランスフォーム砲の一斉射撃が<タクヴァリオン>のコースを 遮らんと接近した。1隻の敵船が爆発して消滅した。 突然、砲火は止んだ。 船は四方八方に散らばり姿を消した。あっという間に <タクヴァリオン>の周りの宇宙は空っぽになった。 呆然としてエクソタアルファから来た男は椅子から立ち上がった。 彼はここで今起こったことが信じられないかのように頭を振った。彼は 振り返って数えた。 「生存者8名」、彼はつぶやいた。 それから彼はカスカルの方に向き直った。 彼はそれと知らずに自分を愛した若い女性の片手をつかんでいた。 反対の手で彼は優しく彼女の顔を撫で、若い女性の美しい目を 閉じた。永久に閉じた。 「いや、たった7名だ。」司令官はつぶやいた。 キャメロットから来た15人が プロフォスで命を落とした。 そのうち一人は救命艇で亡くなった。 しかし、この一人の死んだ女性はカスカルにとって最悪であった。 彼女の手が彼の手をずっときつく握っていた瞬間を彼は決して 忘れないだろう。 「愛している、おかしいかしら?」彼女はささやいた。 彼女は痛みを感じていなかった。薬品はその点は確かに効き目があった。 しかし、それにもかかわらず、彼女は自分の最後が近いことをおそらく 感じていた。 「それなのに、貴方のことを殆ど知らないの。」 「しゃべってはいけない。」彼はささやいた。「君は助かる。 <タアクヴァリオン>に戻れば・・・。」 彼女は指を彼の唇に置き、それから彼の頭を自分に引き寄せた。 彼は彼女の軟らかい唇を自分の上に感じ、涙が流れないように 目をかたく閉じた。 彼女の抱擁がゆるくなったとき、涙に抗うのは止めた。 彼は彼女を堅くだき、彼女の頭が椅子のクッションにあたらないように した。実際、意味の無い動作だった。彼女はもはや何も 感じることが出来なかった。彼女は死んだ。両親と再会する 為に旅立ったが、テラナーがそれを知ることは無かった。 彼は彼女のスリップを腰当てに優しく入れ、それからトークに向かい合った。 「たった7人だ。」その女性の目を閉じてから、もう一度彼はささやいた。 良く言われることだが、彼は考えた、一人の死者は悲劇だ。 100万人の犠牲者は統計上の数字にすぎない。 カスカルはこれまでにも多くの人々が死ぬ様を見てきた。 しかし、たった今まで、死が彼にとってこれほど無用で語り尽くせないほど悲しかった ことはなかった。たった一度だけ、一人の人間の死が本当に彼の心を引き裂いたこと があった。それはヘイブン(Heaven)、時空のひだの中の人工惑星でのことだった。 そこで、カスカル、トーク、そして<ヴィアー・ポンテナー>の乗員は 蛇種族カッサロの捕虜となった。当時、彼の妻は脱走中に死んだのだった。 彼はこの考えを押し殺そうとした。 「コースをキャメロットに。」彼はがらがら声で命じた。ゆっくりと救命艇を 離れた。他に何も付け加える言葉が無かった。
悲惨な犠牲者が出たものの、ジョーク・カスカルはプロフォスから 7人のキャメロット人たちを救い出すことが出来た。 関連惑星の政府の支持は微々たるものであった。 その間、ソマール人サムはモードレッドの手がかりを見つけるという 希望を胸にスティフターマン第三惑星(Stiftermann III)に 向かった。より詳しくはギドー・エッカート(Guido Eckert) の手による第4巻「7つの顔を持つスパイ」で語られるだろう。 そのエピソードは1999年9月5日に貴方の元に届けられるだろう。 (c) 1999 PROC All rights reserved. ドルゴンサイクルは非商用のファン作品である。 主編集:Holger Ho"pfl、翻訳:Holger Ho"pfl、評論:Jean Coulombe、 カバー画:Andreas Roch、著作:Ralf K痓ig。 ペリー・ローダン宇宙のあらゆる権利はVPM in Rastatt, Germanyに属する。 |
|||||||